こんにちは、彩桜です。
みなさんは、ヤングケアラーという言葉を聞いたことはありますか?
私は、数年前にニュースで初めて耳にしました。内容を聞いてみると、実は私もヤングケアラーだったようです。
今回は、ヤングケアラーについてや、自身が体験したことを書いてみたいと思います。
ヤングケアラーとは?
ヤングケアラーとは、なんでしょうか?
通学や仕事のかたわら、障害や病気のある親や祖父母、きょうだいなどの介護や世話をしている18歳未満の子どものこと。
(Wikipedia)
中学生が、家族のお世話をする
私の経験は20年以上前の話です。病気の母と3歳の弟のお世話をしていました。
母が病気で入院し、当時弟は3歳、私は14歳でした。中学校2年~高校1年(半年間)の3年弱、2年半という短い期間でしたが、弟の世話をしていました。
学校の帰りに弟の保育園へ迎えに行き、スーパーで食材を買って、夕飯を作って父を待っていました。高校は遠方だったので、入試の日は、弟を高校近くの一時保育へ預けて受験に行ったのを覚えています。
ただ、私は一人で弟を見ていたわけでなく、父と姉と分担していたという感じでした。当時は、苦痛というわけでも嫌だということもなく。(たまに、めんどくさいと思う時はあったけど)
私の隣には、いつも弟が居たと思います。
その時は、「お母さん」を疑似体験して楽しかったです。他の子と違う自分が、特別な気がしていました。小さい優越感があったのかもしれません。褒められるのも嬉しかったですし。
いまだに弟には、姉目線というより母目線に近いかもしれません。
家族のケアをしていて困ったこと
弟の預け先と、保育園への迎え
父が手続きしていたので、複雑な内容は知らないのですが、弟の預け先は困っていたと思います。田舎で保育園が少なかったので、父や私が帰ってくるまで預かってくれるところが、なかなか見つかりませんでした。
数日間だけ、少し遠い保育園までバスに乗り、迎えに行った記憶があります。道に迷って近所の人に助けて貰いました。
保育園へ送っていくのは父でしたが、帰りは迎えに行けないので、私が行きました。
帰りは遅くならない部活に入っていました。部活は楽しかったから時間制限があるのが、ちょっと寂しかったです。
平日遊びに行けない
父が休みの日曜日にしか友達と遊べませんでした。とはいえ、私はインドアで友達も少なかったので遊びに行かなくても困っていなかったです。ただ、世界は狭くなりがちでした。
金銭的なこと、急なことの対応
母の入院費と弟の保育園費で、家計の負担は大変だったと思います。
父は残業も全部断っていた様でした。朝も弟を送ってから仕事へいくので、少し遅れるとか交渉していたんじゃないでしょうか。私の知らない所で、たくさんの問題に直面していたはず。
弟は滅多に熱を出さなかったので「迎えに来てください」コールが、ほとんど無かったなぁ。
病院へ行くとき等の移動
田舎で、かかりつけ小児科が遠方だったので、病院へ行くときは一緒に徒歩&バスで行っていました。弟に「疲れた」と座り込まれたときは、一緒にしょんぼりしてました。
弟の復活を待つ。私の気が長いのは、そこで培われたのかもしれません。
とはいえ、つらい記憶だけではありませんでした。一緒に手をつないで歩いたことも懐かしいです。ちっちゃい弟の楽しそうな顔とか、帰りに普段食べないハンバーガーを買って食べたりして。いつもと違う日常も楽しんでいたと思います。
ヤングケアラーの問題点

ヤングケアラーには、次の問題点があります。
私の場合、家庭の事情を抜きにして学業に専念したかというと、しなかったのではないかと思いますが…。

勉強嫌いだった?
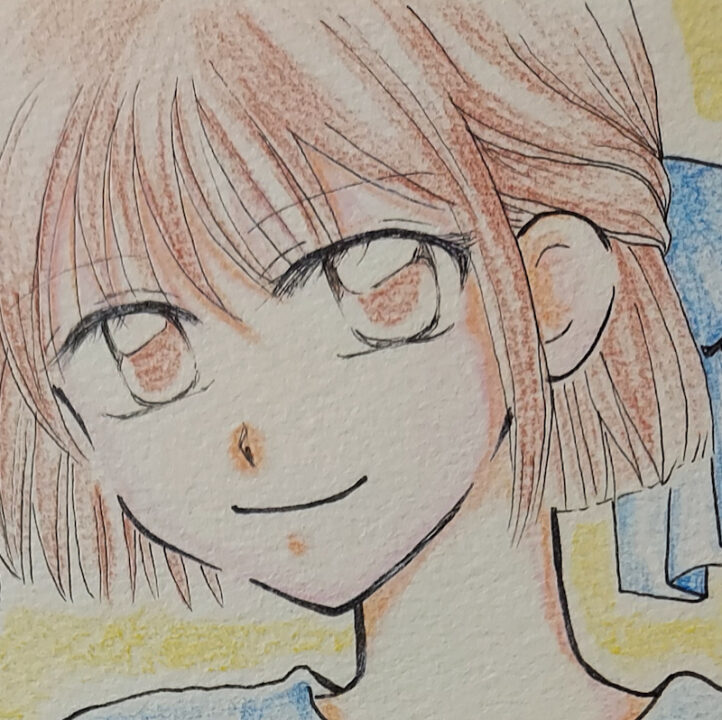
嫌いじゃないよ。普通。
適度にしてたって感じ。漫画描いてたから、そっちが楽しくてさ。

何でもハマるとずっとやってるよね。
しかし、受験勉強に集中しずらいという環境ではあったと思います。時間が取れずに進学を諦めてしまうケースも多いのではないでしょうか。
「相談していい」と発信することが大事
家族のケアをすることは悪いことではありません。
私も良い経験になりました。ただ、誰にも相談できず追いつめられてしまうケースもあると思います。「学校の先生だったり、身近な大人に相談しても良いんだよ」と発信するのは大切です。(私は父に相談できてていたので、そんなに負担を感じてなかったです)
私の場合、当時学校の先生が知っていたのかどうか、わかりません。父が伝えていたか、私の言動で薄々気づいていたか。ただ、そういうことを話したことはありませんでした。
「学校に相談することではない」と勝手に思っていました。
そして、それが私にとっての普通でした。「私以外にもみんな言わないだけで、そういう家庭は、たくさんある。がんばろう」って思ってた気がする。
「一般家庭」「普通の家庭」という言葉は曖昧で、外から見ただけでは分からないです。私は結婚してから、「夫の家庭」と「私の家庭」が、かなりズレていることを知りました。
おわりに
介護などは、お金の問題もあり、まだまだ「家族でケアするのが当たり前」な社会があります。
しかし、核家族化や高齢社会が進む中、若い世代がどんどん負担を背負っていくのは限界があります。社会問題として、これから大人たちがどう向き合っていくのか、支援していけるか。福祉は、たくさんの課題が山積みです。



コメント