こんにちは、彩桜です。
みなさんの家には、どんな家電がありますか?
家電が普及したのは、ここ60年くらいです。
ふと、家電がなかった時代の生活はどうだったのだろう?と思いました。
時々、父(70歳)が家電がなかった頃の話をしてくれます。今回は、父の話に基づいて1960年ごろの田舎の生活を書いてみたいと思います。
- 家電がない生活って?
- 昭和の田舎暮らしに興味がある
そんな方に。
※ちなみに父の幼少期の記憶を掘り返したので、数年の記憶違いがあると思います。
家電がない生活
冷蔵庫がない
冷蔵庫がないと、必然的に「食」のライフスタイルは変わります。父が子供のころは、その日に買ったものは、当日に食べきることが多かったそうです。
近所に商店があり、そこには冷蔵庫があったそうで、ジュースは買ってすぐ飲んでいたとか。
そんな父の食生活は、こんな感じ。
- 麦ごはん
- 肉はあまり食べないが、たまに商店で買う
- 魚は釣って食べる(釣れる環境なら)
- 豆腐は豆腐屋さんで必要な分だけ買う
- たまごは一個ずつバラ売り
- 野菜は庭で育てる。物々交換が多い
- スイカは井戸で冷やす
- コロッケを買いに行くのが楽しみ
- ジュースは商店で買い、すぐに飲む
- アイスは露店で買う

コロッケ!俺も食べたい。
上段に大きな氷をいれて、下段を冷やす「保冷庫」のような物はあったようです。
電気で冷やすわけではないので、氷がとけたら冷えません。大きなクーラーボックスみたいな感じでしょうか。
当時、冷蔵庫がなくても、どうにか生活できる気候だったというのも大きいかもしれません。
食材をその日に食べ切る生活は、私が生まれてからも継続していました。我が家の冷蔵庫は、小さかった記憶があります。
洗濯機がない

洗濯は、洗濯板で手洗いです。脱水するためだけの機械があったのだそう。
電気ではなく、手動でぐるぐる回すタイプです。蛇口をひねったらお湯が出てくる時代ではないので、寒いときはお湯を沸かしたり、かなり不便だったと言えます。
- バスタオルはない。手ぬぐいを使用
- 肌に直接触れるもの以外、毎日洗わない
- 外に洗濯を干す場所が広くある
タオルのフカフカ生活ができないのは、とてもツラいです。洗濯板でバスタオルを洗濯したら、絞るのが大変そうですね。
昭和初期の洗濯事情は、とても不便だったと言えるかもしれません。洗濯機は、すばらしい家電です。
家電を購入したのはいつ?金額は?
この辺は、父の記憶が多少違うかもしれません。
父の家は裕福では無かったので、購入したのは一般より遅かったのではないでしょうか。田舎の方が、なんでも普及は遅いものです。
当時の値段としては、冷蔵庫が1万5000円ぐらいで、TVは5,0000円ぐらい。(もっと高いものもある)
当時の月収は平均30,000円程度と言われています。田舎なので、もっと低いかもしれません。
TVや冷蔵庫を買うためには、目安としてTVは給料の2か月分、冷蔵庫は給料の半分必要になります。
お風呂はどうしていた?
今は、オール電化でお風呂も電気という家庭も多いです。
お風呂はどうしていたのでしょう?
- 山で薪を拾ってきて、沸かす。
- 井戸から水をくんで運ぶ。
水道を引いたのは、父が18歳くらいの時だそう。家の前まで水道は整備されていたけど、「あとは各家庭で工事してね」という感じだったそうです。父が工事したとのこと。
昔の人は何でもするなあ。
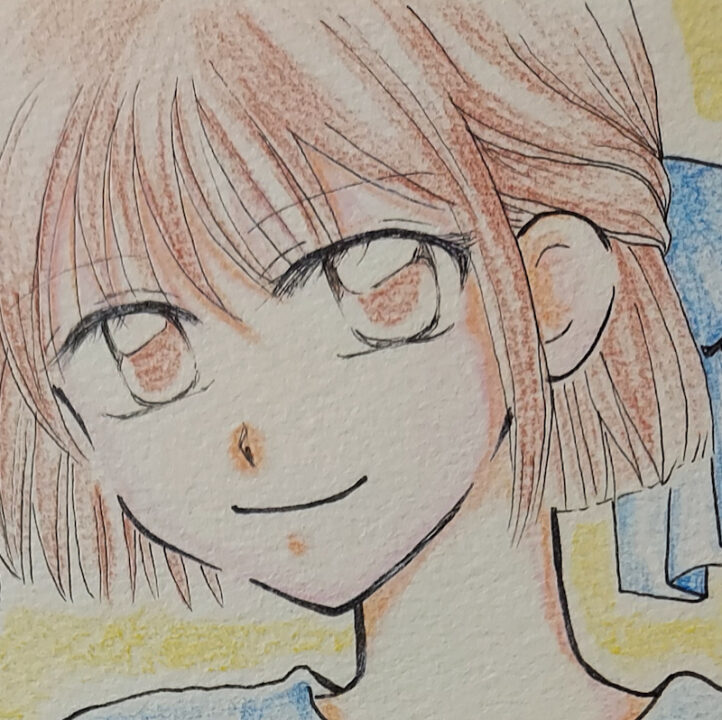
そういえば、祖父母の家に遊びに行ったとき
井戸があったなあ。
ポンプの井戸、かっこよかった。
もらい風呂(風呂を借りに来ること)もあったとか。
父の実家は、大きめのお風呂を設置したので、近所の人が入りに来ていたらしいです。現代で近所の人が自分の家の風呂に入りに来たら、びっくりしますね。

俺は、風呂が嫌いです。
近所づきあいは、深そうです。「普通に調味料を貸し借りしていた」と聞いて、不思議な気持ちになりました。
エアコンは、実は新しい家電
エアコンが一般家庭に普及したのは、1990年以降です。私が中学生の時くらいですが、その頃は窓に取り付けるタイプのクーラーを使用していた記憶があります。
現在は熱中症も心配なのでエアコンは必要です。
高齢者はエアコンの風が苦手な人も多いです。慣れていない、というのもあるのかもしれません。
おわりに
たった60年くらいで家電が一気に普及しました。
今は、洗濯も全自動。食洗器や、全自動掃除機まである家庭も多いです。これから100年後、どうなっているのでしょう。ロボットがやってくれる時代になるでしょうか。
家電がないという生活は、なかなか想像できないかもしれません。
便利で、ありがたい時代だと思います。
あたりまえのように日常にある電気、たくさん感謝して大切に使いたいですね。
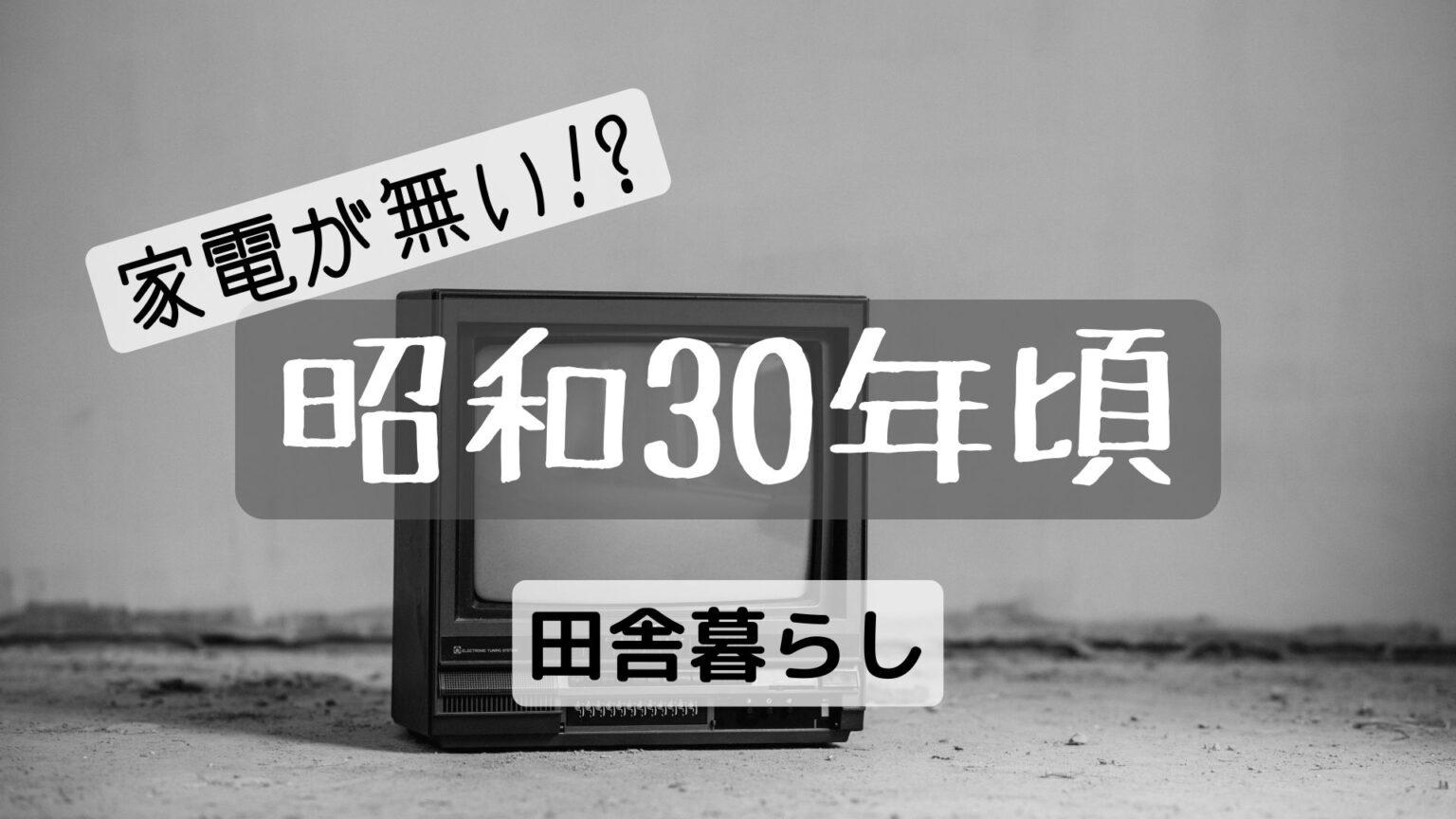
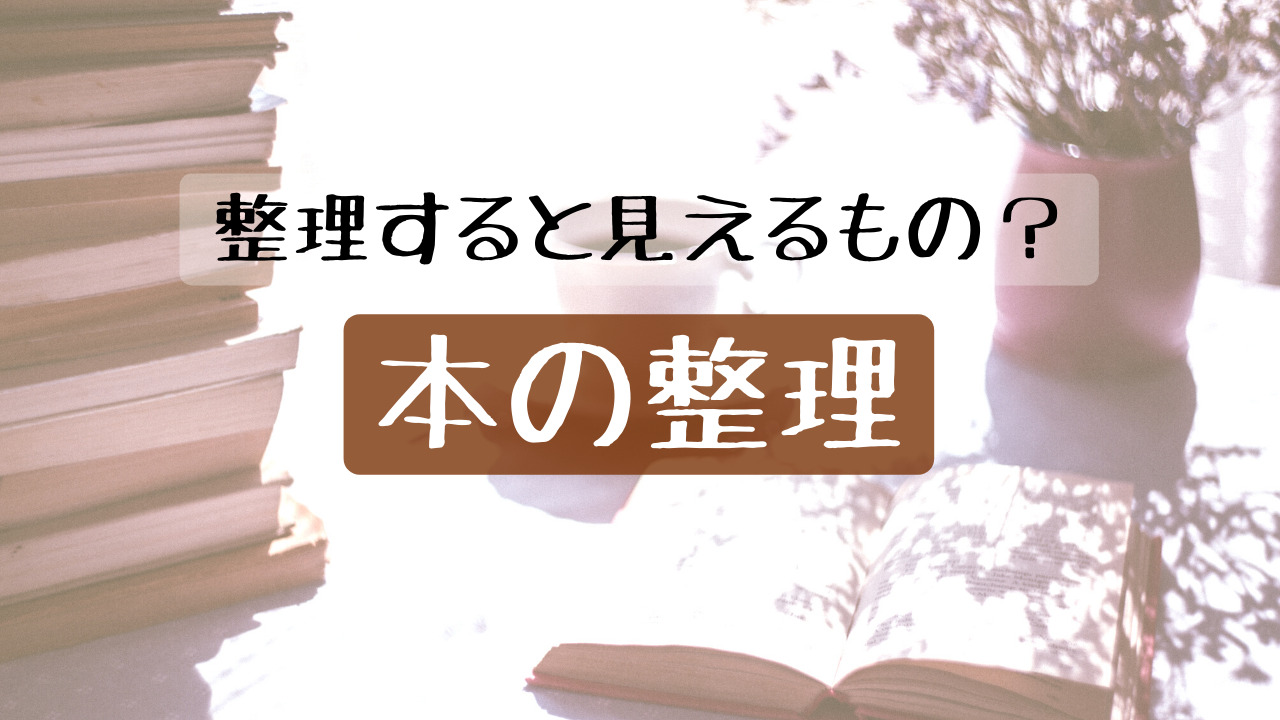

コメント